マーケティングはどんなことをするのか、起業前や起業仕立ての頃は理解に苦しむと思います。またマーケティングの必要性が仕事で出てきたときに、言葉だけは聞いたことがあっても具体的な取り組み方がわからなければ、戦略や戦術を練ることができません。
今回は初心者の方でもわかりやすいベーシックな事業で使えるマーケティングのフレームワークを7つお伝えします。それぞれで使用するタイミングが異なるため、その点も踏まえて解説していきます。
PEST分析

PEST分析はマーケティングの第一人者であるフィリップス・コトラーが提唱したフレームワークで、マクロ環境を4つの視点から分析するものです。
以下のそれぞれの頭文字をとったものになります。
PEST分析
- P:Politics(政治的要因)
- E:Economy(経済的要因)
- S:Society(社会的要因)
- T:Technology(技術的要因)
マクロ環境とは、自社でコントロールすることが難しい外部環境のことです。ビジネスは政治や国内外の経済状況によっても大きく左右されるので、マクロ環境を分析することはとても重要になります。
この分析により、自社のビジネスに影響を与える可能性のある外部要因を包括的に把握できます。例えば、環境規制の強化(政治的要因)が自社製品の開発方針に与える影響や、高齢化社会(社会的要因)による新たな市場機会の発見などが可能になります。
ちなみにPEST分析はマーケティングの初期段階で行うものになります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
5C分析

5C分析は5つの視点から業界の環境分析を行うフレームワークで、自社のビジネスを取り巻く環境を客観的かつ多角的に評価し・整理する時に有効です。
5C分析
各分析については以下のようなことを調査・検討します。
市場・顧客
業界の市場規模や市場の成長性、顧客のニーズ等を把握します。
競合
現状のシェアや各社のポジショニング、特徴を把握します。
自社
経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)や自社の経営理念、強み・弱みなどを洗い出します。
中間顧客
自社と同じで、協力業者の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)や目指す方向性、強み・弱みなどを把握します。
社会環境
ビジネスを取り巻く外部環境を把握し、動向や変化の兆しを適宜確認できるようにしておきます。
この分析により、自社を取り巻く環境を総合的に理解し、効果的な戦略立案が可能になります。例えば、顧客ニーズの変化と自社の強みを組み合わせた新製品開発や、競合他社の動向を踏まえた差別化戦略の立案などに活用できます。
元々は上3つで3C分析と言われていましたが、デジタル化が進んだことから、3Cでは分析しきれなかった部分を5Cを利用して分析するようになっています。
5C分析はマーケティングの初期段階で行われ、実施後はSWOT分析と併用する流れが一般的です。
ファイブフォース分析

マイケル・ポーターが提唱したこの分析は、5つの視点から競争要因から業界構造、自社の魅力などを分析するフレームワークになります。複雑な競争関係を把握、脅威を発見するときに役立ちます。
ファイブフォース分析
①競争業者
既存の競合他社間での競争のことで、企業の規模が影響していきます。競争が激しければ、利益を生み出しにくくなります。
②買い手
商品を購入してくれる顧客の交渉力による脅威のことです。値引きや追加サービスなどの要求により利益率が低下する可能性があります。
③供給業者
仕入れ先の脅威のことで、仕入れ先の影響量が大きいほど仕入れコストが高くなる可能性があります。仕入れを1社に頼っていると特に影響力が大きくなってしまいます。
④新規参入業者
参入障壁が低いほど、新規参入業者が増える脅威があります。飲食店などは新規参入しやすいですが、インフラ関係は規制があり障壁が高いと言えます。
⑤代替品
既存商品が代替品によって顧客ニーズを満たしてしまう脅威のこと。CDがストリーミング配信によって購入されなくなった例が挙げられます。
ファイブフォース分析は現時点での自社の優位性や課題点を明確にし、戦略を練ることが目的となってきます。業界の構造的な特徴を理解し、自社の戦略的ポジションを明確にするのです。参入障壁が低い業界では差別化戦略が重要になるなど、競争戦略の立案に役立ちます。
ファイブフォース分析についてはこちらで詳しく解説しています。
SWOT分析
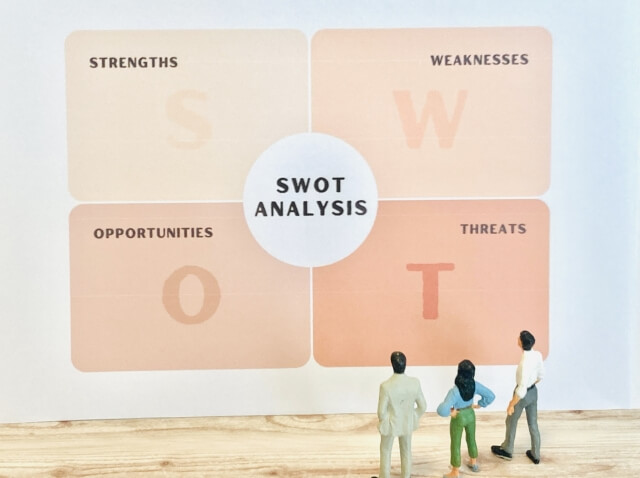
外部要因・内部要因を4つのマトリクスに分割し自社の課題・機会を発見するフレームワークです。企業の問題や優位性を明確にすること以外にも、個人の目標設定で使用することもできます。
SWOTブンセキ
自社の現状を客観的に把握し、戦略立案に活用できるのがSWOT分析です。例えば自社の強みと市場機会を組み合わせた成長戦略や、弱みを克服して脅威に対処する防衛戦略などを考案できます。
実施の際は自社の強みと弱みが、客観的にみてもそうなのかを判断して進めなければ、的外れな分析となってしまうので注意が必要です。
なおSWOT分析はクロスSWOT分析まで行うと、現状の解決の糸口が見えてくるようになります。

STP分析

STP分析はターゲット市場を明確にし、効果的なポジショニングを行うためのフレームワークです。自社が戦う市場を特定するために重要となります。
マーケティングのポイントとなる「誰に」「何を」の部分の分析を行い、商品やサービスを位置づけしていきます。
STP分析
セグメンテーション
「地理的変数」「人口動態変数」「心理的変数」「行動変数」を用いて区分します。
ターゲッティング
細分化された市場をもとにどこを狙うべきなのか、市場の成長規模や自社のコンセプトから見極めます。
ポジショニング
市場の優位性をいかに保つかが重要となるため、ポジショニングマップを作成し、他社と比較しながら立ち位置を考えます。
限られた経営資源を効率的に活用し、効果的なマーケティング戦略を立案できます。例えば特定の年齢層や所得層にフォーカスした商品開発や、競合との差別化を明確にしたブランディングなどに活用できます。
STP分析についてはこちらの記事でより詳しく解説しているので、参考にされると良いでしょう。
7P分析

7Pは マーケティングミックスの要素を7つの視点から検討するフレームワークです。こちらもフィリップス・コトラーが提唱したものです。7Pは伝統的4Pに加え、サービス特有の3Pを加えたものです。
マーケティングミックスの要素を7つの視点から検討するフレームワークです。こちらもフィリップス・コトラーが提唱したものです。7Pは伝統的4Pに加え、サービス特有の3Pを加えたものです。
4Pは製品などモノを中心としたフレームワークでしたが、サービス化が進むことで7Pの考えが現在は主流となっています。
7P分析
7Pは製品やサービスの提供に関わるすべての要素を総合的に検討し、一貫性のあるマーケティング戦略を立案できます。例えば高級ブランドイメージを維持するための価格設定や、顧客満足度を高めるためのサービスプロセスの改善などに活用るるとよいでしょう。
この7P分析はSTP分析で立てた戦略を具体的にして実行に移します。
バリューチェーン分析

バリューチェーン分析もマイケル・ポーターが提唱したフレームワークです。
バリューチェーンとは日本語で言うと「価値連鎖」と表現されており、原料から製造・販売、そして消費者に届くまでの一連のながれだけでなく、それを裏で支える開発・経理・労務管理なども含まれます。企業の活動を価値創造の連鎖として捉え、各活動の貢献度を分析するためい使用されます。
主活動
- 購買物流
- 製造
- 出荷物流
- マーケティング・販売
- サービス
支援活動
- 全般管理
- 人事・労務管理
- 技術開発
- 調達活動
バリューチェーンはモノやサービスにどのような価値が付加されたのか。またどのように消費者まで供給されているのかを分析するので、競争優位性の視点から見たときに、自社の劣る部分はどこなのか、どのプロセスで問題が起こっているのかを明確にすることができます。
例えばコスト削減の余地がある活動の特定や、顧客価値を高めるために強化すべき活動の明確化などに活用できます。
おわりに
7つのマーケティングをご紹介してきましたが、どのフレームワークをどんな時に使用するか理解いただけたでしょうか。その時々でフレームワークを利用して自身の事業に優位性がでるように戦略を立てることは、事業継続をしていくうえで大切です。
ぜひ一度自分の事業に当てはめて考える時間を設けることをオススメいたします。頭をつかうことこそ経営者の仕事ですからね。


