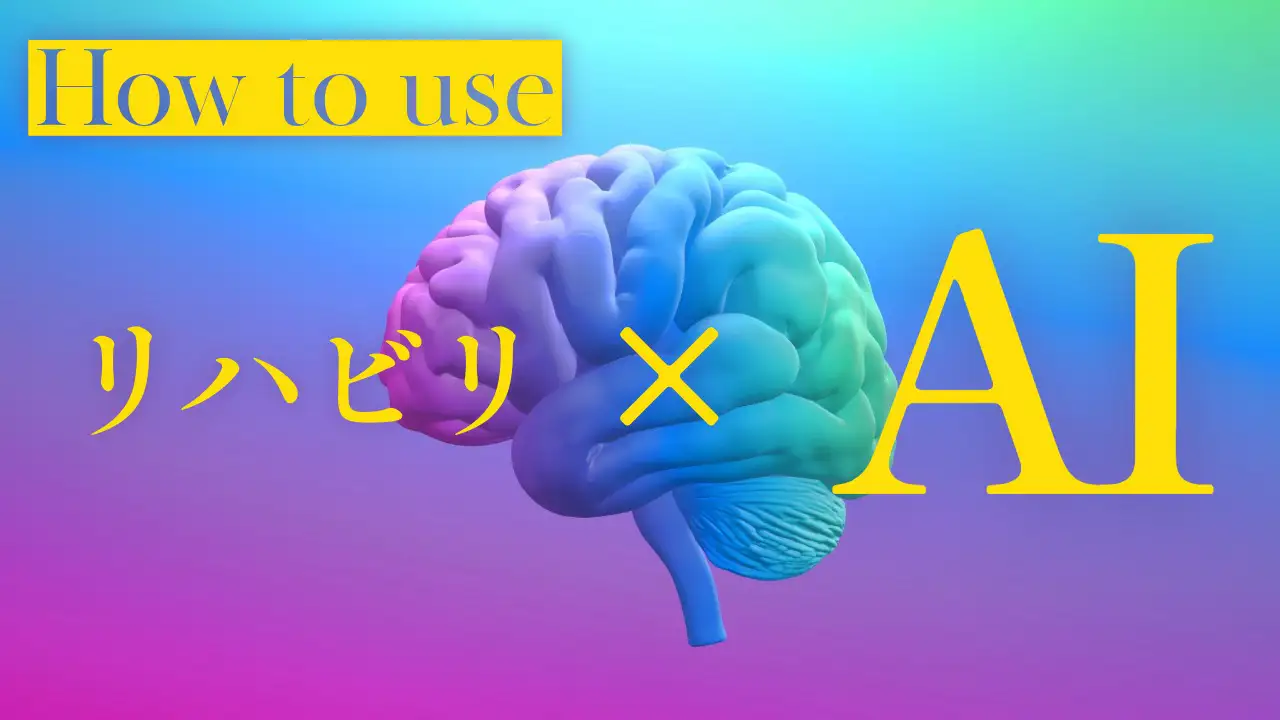「AIが仕事を奪う」そんなニュースや記事を見たことありませんか?
定期的に無くなる仕事が報道されていますが、リハビリテーション専門職はそれに動じる必要はありません。リハ職にとってAIは私たちの仕事を脅かす存在ではなく、むしろ私たちの専門性を最大限に引き出し、臨床の質を劇的に向上させる最高の「相棒」といっても過言ではありません。
AIを使いこなすことは、今後パソコンで作業するのと同じくらい当たり前になってきます。この記事では、難しい話は一切抜きにして、明日からあなたの臨床が劇的に変わる、個人で使える具体的なAI活用術を厳選してお伝えします。
なぜセラピストがAIを使うべきなのか?

「AIで仕事が楽になる」確かに事実ですが、これは本質ではありません。
私たちが今、AIを学ぶべき本当の理由は、セラピストという専門職の価値を社会の中でより高め、進化させるためです。ここでは具体的な理由を3つお伝えします。
①単純作業から解放される
私たちは日々、膨大な「作業」に追われています。日々のリハビリ記録、患者さんや利用者さんの情報収集、リハビリ計画書やサマリーなどの書類作成。これらは重要ですが、私たちの専門職が本来時間を長く割いて行う作業ではありません。
AIができること、人ができることを分けて、これからは本質的な業務により労力を割いていくべきなのです。
-
AIができること: 膨大な情報の検索、データの整理、文章のドラフト作成
-
人間にしかできないこと: 患者さんの表情や声のトーンから不安を読み取ること、触診で組織の変化を感じ取ること、データと目の前の患者さんの人生背景を統合して最適なアプローチを判断すること、そして、信頼関係を築き社会復帰を支援すること
AIは私たちを煩雑な「作業」から解放してくれます。それによって生まれた時間と精神的な余裕を、私たちは人間にしかできない人間味のある対応や、より高度なリハビリテーションの提供に注力できるようになります。
②データで裏付け、質を高める
優秀なセラピストは、長年の「経験と勘」を持っています。これは臨床の現場で活躍する著明な先生方をみればよく分かります。しかし、経験と勘はその人の頭にしかなく、その素晴らしい”暗黙知”を他のセラピストに簡単に共有することはできません。
「研修会で習ったから」「勉強会で勉強したから」くらいでは、すぐすぐ身につくものではないのです。
しかしこの状況を打開するために、世界中にある客観的なデータで知識や経験を補うことができたらどうでしょうか?
「この患者さんには、このアプローチが効きそうだ」というあなたの直感に対して、AIは瞬時に世界中の論文から関連エビデンスを提示してくれます。これによりあなたの経験・勘が、科学的根拠によって裏付けられ、介入の確信度を格段に上げることができます。
また入院患者さんのデータをAIを用いて予後予測させることも可能です。

このような主観的な説明は客観性がなく、経験によって予後予測の精度も変わってきますが、

「データ上、80%の確率でここまで回復が見込めます」
AIを使うとこのように具体的な数値を提示して客観的にお伝えすることができるようになります。
この具体的な数値を提示できることは、あいまいになりがちな臨床において、患者さんやご家族にとって、より深く納得してリハビリに参加いただけるようになります。
③セラピストとして価値を高める
10年後のリハビリテーションの現場はどうなっているでしょうか? おそらく、AIを活用することが当たり前の世界になっていると私は推測します。
電卓が登場したとき、そろばんを使って計算をする事務員はいなくなりました。実務的な計算速度と効率性を大幅に向上させたからです。それと同じように、これからのセラピストは、AIというツールをいかに使いこなし、自身の専門性と融合させるかが問われます。
AIを「仕事を奪う脅威」と捉えるか、「自らの能力を拡張するツール」と捉えるかで、5年後、10年後のセラピストとしての価値は大きく変わってきます。
どうせ将来的に使う時代が来るのなら、今のうちから活用して周りとの差を広げるのもありだと思います。
あなたの臨床を変えるAI活用術5選

AIの重要性については前述しましたが、AIは種類も多く、「ChatGPTくらいしかわからない」「どんなふうに使えばいいかわからない」「嘘をつくと聞いたことがある」など活用において疑問に思う方も少なくないと思います。
「何から使えばいいか分からない」という方も含めて、ここでは今すぐ無料で始められる、簡単で効果的な方法を5つご紹介します。
1.情報整理と資料の保管場所として活用
膨大な量の論文やガイドライン、PDF資料を調べてダウンロードしたはいいけれど、活用できていない。あるいはどこにいったかわからないなど管理で困った経験はありませんか?
資料の検索はAIでもできますが、Googleの「NotebookLM」を使えば資料の保管と同時に、情報整理まで簡単に行えます。
使い方
できること
-
瞬時に要約:「この20本の論文の要点を3行でまとめて」
-
ピンポイントな質疑応答:「脳卒中後の上肢麻痺に対する最新のアプローチについて、これらの資料から教えて」
-
アイデアの壁打ち:「新しい研究テーマのアイデアを5つ提案して」
一つ一つ論文を読むのにはかなりの時間がかかります。かといってAIを活用して検索した情報はハルシネーション(事実ではない情報を生成してしまう現象)を含んでいる可能性もあるため、特に医療業界では事実確認を行う必要もあります。
ですがNotebookLMは自身の持つデータをもとに回答を生成してくれるので、ハルシネーションが非常に少なくなります。
疾患別の治療ごとにファイルを分けておけば、それぞれの患者さんの評価や治療プランを簡単に組み立てることも可能となります。
情報収集の時間が大幅に削減され、リハビリの「質」を上げることのできる「NotebookLM」をまずはセラピストの方は使っていただきたいです。
NotebookLMについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
-

-
参考NotebookLMで社内の生産性がUP!AIが知的作業を根底から変える
毎日大量の情報に囲まれ、知識を上手に活用して新しい価値を生み出すことが難しくなっています。そんな現代でGoogleが開発したAI搭載ノートツール「NotebookLM」が、私たちの知的生産性を大きく向 ...
続きを見る
2.海外論文がストレスなく読めるAI翻訳
新卒3年目くらいのころ、先輩から英論文を読むように指導されて毎週翻訳したものを発表する時間がありました。大変な経験でしたが、そのおかげで英論文を読むことへの抵抗は減りました。ただ私のような経験をした方はそう多くないでしょう。「英語論文はムリ」という方の方が多いと思います。
でも安心してください。今は海外の論文を翻訳して、さらに要約までしてくれます。聞けば必要な情報だけを教えてくれることもできるので、AIを活用すれば言葉の壁はなくなります。
ポイント
NotebookLMを使えば、ポッドキャストのように論文の内容を日本語で聞くこともできます。耳で聞くことができるので、移動中などにもとても便利です。
エビデンスレベルの高い資料はほとんど英語で記述されています。だからこそ、AIを活用して英論文への抵抗を減らすことは、セラピストとしての自身の成長にとっては不可欠だと思ってください。
3. 論文執筆の手助けになる
海外論文を読むだけにとどまりません。論文を執筆する難易度もグッと下げてくれます。セラピストで論文を執筆したことのある方は多くはないでしょう。ですが学会発表や論文執筆は、セラピストとしての価値を高める重要な活動です。
しかしながら多忙な臨床の合間を縫って論文を執筆するのは相当な苦労を要します。AIはそんなあなたの研究活動をサポートしてくれる相棒としても活躍します。
活用の流れ
-
文献検索: 関連キーワードから、読むべき重要論文をリストアップ
-
先行研究の要約: 膨大な数の論文から、あなたの研究に必要な情報だけを抽出・要約
-
考察の壁打ち: 結果の解釈や考察について、AIとディスカッション
-
英文校正・作成: 苦手な英文抄録も、ネイティブレベルの自然な文章に
実際、AI英文校正・執筆支援ツール「PaperPal」は、学術論文の執筆時間を「最大で50%削減」すると謳っています。専用のAIでなくても、論文執筆のどのフェーズでもAIは活用できるので、論文執筆のハードルは以前より大幅に下がっていると言えるでしょう。
4. 書類作成業務からの解放
日々の記録やサマリー、リハビリテーション実施計画書の作成に、どれだけの時間を費やしていますか? ChatGPTやGeminiなどの生成AIを使えば、その負担を大幅に軽減できます。
例えば退院時サマリーを作成することをイメージしてみてください。電子カルテから情報を引用することができずに、WordやExcelでサマリーを1から作成することを考えると、気分が滅入りませんか?
そんなとき以下のようなプロンプトをAIに投げると、ドラフトを作成してくれるのでだいぶ楽になると思います。
「以下の患者情報に基づき、回復期リハビリテーション病棟の退院時サマリーのドラフトを作成してください。#患者情報: 80代男性、右片麻痺、FIM運動項目〇点、認知機能低下あり…」
もちろん、AIが作成したドラフトはあなたの専門的な視点で修正・加筆することが必須で、個人情報を入力しないことに注意する必要があります。
ですがゼロから文章を組み立てる手間が省けるだけで、長時間の残業をして書類を作成する必要がなくなり、もっと患者さんのためになる時間を確保できるでしょう。
もともとサマリーの書式がある場合は、そちらをAIに読み込ませて、その項目にあった情報を生成してもらい、コピペするだけでも作業はだいぶ楽になるはずです。
メモ
サマリーだけでなくNECと北原病院グループによるリハ計画書作成の実証実験の結果をみると、作成にかかる時間は60%も短縮され、計画書の質も向上したことが報告されているほど、AIは業務の身近な存在になってきています。
書類作成でもう1つ多いのが、院内研修会用の資料や学会発表用の資料など、プレゼン資料を作成することではないでしょうか。PowerPointを使って資料作成をした経験のある方も多いでしょう。
この作業はかなりの時間を要します。根拠となる論文を探して、スライドを1枚1枚作成するのは大変な作業ですが、現在はAIでスライドを自動で作成できる「Gamma」「Genspark」「Felo」などのツールもあるので、作成にかける時間は大幅に削減でき、デザイン性の良いものを作成できるようになっています。
5. 臨床の「引き出し」を増やす
「この患者さん、なかなか改善しない」「別のアプローチはないだろうか?」臨床で行き詰まることは誰にでもあります。そんな時、先輩に聞くよりももしかしたらAIの方が優秀な回答をしてくれるかもしれません。あるいは先輩に相談する前にAIに相談してから、アドバイスを求めるといった使い方もできるかもしれません。
AIにリハビリの相談をするときは以下のような使い方を心がけましょう。
相談のコツ
-
個人情報やプライバシーに最大限配慮し、情報を抽象化・一般化する。
-
「〇〇という病態の患者に対して、一般的に考えられるリハビリテーションアプローチの選択肢を、理論的背景と共に10個挙げてください」
-
「◻︎◻︎の状態にある症例に対して、△△という手技を行うことの禁忌やリスク、エビデンスレベルを教えて」
アイデア出しは、AIを最も活用するのに適しています。10個でも、100個でも嫌がることなく、AIはあなたの知識や経験だけでは思いつかなかった新たな視点やアイデアを提供してくれます。だからこそ使う価値があるのです。
AIとリハビリの未来

ここまでは「今すぐできること」を紹介しましたが、AIの進化は止まりません。すでに、私たちの臨床を根底から変えるような技術が実用化され始めています。
その一つが「AIによる予後予測」です。ソニーが開発したAIは、回復期リハビリテーション病棟の患者データ(FIM、年齢、麻痺の重症度など)を基に、退院時の歩行自立度を非常に高い精度で予測します。
これが何を意味するかというと、先にも少し述べましたが、客観的なデータに基づき、患者さんやご家族に、より納得感のあるリハビリ目標を提示できる点です。「このリハビリを続ければ、これくらいの確率で歩けるようになる可能性があります」といった、具体的で希望の持てる説明が可能になります。
また AIが予測した未来像を基に「その未来を実現するために、どのようなプログラムが最適か?」をセラピストは考え、実行する。予後予測という”作業”から解放され、よりリハビリ職として求められる「技術」にフォーカスが当たっていくと思います。
AIが土台となるデータ分析や予測を行い、私たちセラピストは患者さん一人ひとりの想いや生活背景に寄り添った、これまで以上に個別化されたリハビリテーションを提供する未来が来ることになるでしょう。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。ここまで読んで、AIに対するイメージは変わったでしょうか?
AIは私たちの仕事を奪うものでは決してありません。ロボットとAIの進化も進んでいますが、リハビリテーションのような仕事はAIには代替が難しいとされています。
面倒な作業を肩代わりし、知識を拡張し、新しい視点を与えてくれるパートナーがAIなのです。だからこそ私たちは技術をこれからはもっと磨くべきです。
もし
-
「自分の領域で、もっと具体的なAIの使い方を知りたい!」
-
「最初の第一歩を、誰かにサポートしてほしい!」
-
「AIを活用した新しいリハビリの形を一緒に模索したい!」
このように少しでも感じていただけたなら、ぜひ弊社(田中)にお気軽にご相談ください。